【日常から非日常まで大活躍!】大型特殊免許とは?
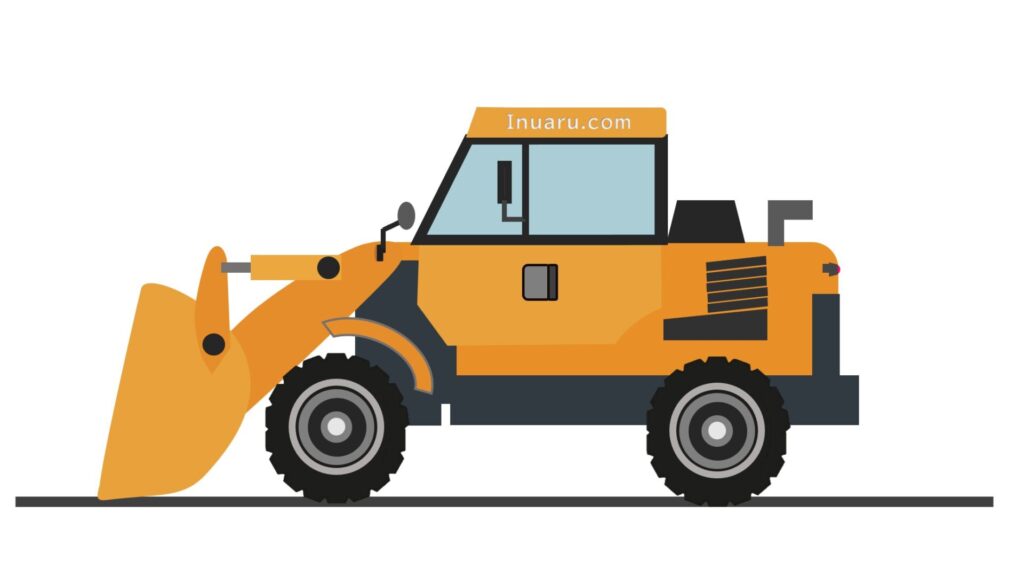
大型特殊車両とは?
大型特殊免許とは、大型特殊免許はその名の通り、特殊な車両を公道で「運転」するのに必要な免許。
あくまでも公道を走らせるための免許証であり、作業をするにあたってはそれぞれの車両に応じた“資格や免許”が別途、必要になります。大型特殊免許をもっていると、その下位車両に当たる小型特殊自動車や原動付自転車(原付)も運転できます。
大型特殊免許で「運転」できる主な車両
1.ホイールローダー

バケットといわれる大きなショベルが車体の前方についており、工事現場でダンプトラックに運搬物を積み込む時に活躍します。近い距離であれば、そのまま運搬物を運ぶことも可能。積雪時の道路の除雪にも活躍。
ホイールローダーに近い乗り物としてブルドーザーがありますが、ホイールローダーはゴムタイヤ、ブルドーザーはクローラー(キャタピラー)という点。ホイールローダーは、公道をそのまま走ることが可能ですが、キャタピラーのブルドーザーは公道を自走することができません。
ホイールローダーを操作するための資格・免許
車両系建設機械運転者が必要となります。機械質量が3トン未満か3トン以上かによって内容が異なります。
〈機械質量3トン未満〉
特別教育(安全衛生特別教育規程で規定された12時間の履修)
〈学科講習科目〉
・走行に関する装置構造、取り扱いに関する知識(3時間)
・作業に関する装置構造、作業方法に関する知識(2時間)
・運転に必要な一般事項に関する知識(1時間)
・関係法令について(1時間)
〈実技講習科目〉
・走行操作(4時間)
・装置操作(2時間)
〈機械質量3トン以上〉
技能講習(合計38時間の学科講習と実技講習)
〈学科講習科目〉
・走行に関する装置構造、取り扱いに関する知識(4時間)
・作業に関する装置構造、作業方法に関する知識(5時間)
・運転に必要な一般事項に関する知識(3時間)
・関係法令について(1時間)
〈実技講習科目〉
・走行操作(20時間)
・装置操作(5時間)
※保有している資格や経験などにより、6時間~38時間とコースが異なります。
2.ラフタークレーン
工事現場などでよく見かける移動式クレーンのこと。1つの運転室でクレーンの操作も車両の運転が可能。ラフタークレーンに近い乗り物としてトラッククレーンがあり、トラッククレーンは道路を走行するための運転室とクレーン装置を設けたクレーンを操作するための運転室が別々。また、トラッククレーンは大型特殊ではなく、大型自動車に分類されます。
ラフタークレーンを操作するための資格・免許
- 吊り上げ荷重0.5t〜1t未満:移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
- 吊り上げ荷重1t〜5t未満:小型移動式クレーン運転技能講習
- 吊り上げ荷重5t以上:移動式クレーン運転士免許
3.トラクター

田植えや草刈り、畝(うね)立てなどの農作業で用いられる車両ですが、実はトラクターはけん引を目的とした車両の総称。トラクター(tractor)の語源は、ラテン語の「trahere(引っ張る)」が由来とか。
私有地内で作業するだけなら、トラクターを操作するための資格や免許は不要ですが、実際は資材を積み込んでほ場まで運ぶことや倉庫からほ場へトラクターで直接移動することが多いので、大型特殊免許があると便利です。
4.除雪車
除雪トラック、ロータリー除雪車、除雪グレーダ、除雪ドーザおよびトラクタショベル、小型除雪車などの種類があります。それぞれの除雪機械に対して、免許と講習受講義務異なります。
5.フォークリフト
車体前方にフォーク(つめ)があり、トラックの荷台に貨物をパレットごと積み下ろしをする車両のこと。一般的によく見かけるのは カウンターバランス式(後方にウエイトがあるタイプ)ですが、倉庫内で良く見かけるのはリーチフォークリフト式。最小回転半径が小さく、車体が停まった状態でもフォークを前後に動かせる点が特徴です。

6.戦車

一般の人が戦車を運転する機会はまずありませんが、実は戦車を運転するには大型特殊免許が必要です。さらに、自衛隊の戦車を運転するためには、「MOS」と呼ばれる自衛隊内部の資格も取得しなければなりません。
普段、目にすることのない戦車ですが、有事を想定した「路上教習」として、公道を走ることもあるそうです(私は見たことがありませんが…)。ただし、50トンもの重量がある特殊車両なので、どこでも走れるわけではなく脱着式のサイドミラーを装着したり、道路面の破損を防ぐために履帯(キャタピラ)にゴムブロックを取り付けたりと、さまざまな対策が必要です。さらに、事前の申請や色々な制約があるそうです。
受験資格
- 年齢: 満18歳以上
- 視力: 左右それぞれ0.3以上、両目で0.7以上(眼鏡やコンタクト使用可)
- 色別識別: 赤、黄色、青の識別ができること
- 聴力: 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)
- 運動能力: 運転に支障がないこと
取得方法
①教習所に通う ※3ヶ月以内に卒業する必要あり
②合宿免許で教習を受ける
③一発試験を受ける
おススメは、①教習所に通うです。
理由①:普通免許で乗れる車とは全くの別物なので、慣れるのに時間が掛かる
理由②:自宅に大型特殊車両がないので、練習ができない
教習所に通った場合の一般的な費用は…、
| 普通免許 | 費用 | 内容 |
| あり | 約10万円 | 技能教習6時限 |
| なし | 約20万円 | 学科教習22時限 技能教習12時限 |
合格率
大型特殊免許第一種の合格率は、約8割!
ちなみに、第二種になると合格率は約3割と難易度が高くなりますが、ブルドーザーや大型の除雪車などを使って旅客運送業務(車両に客を乗せて運行)をすることはほぼ、ありませんので免許を取ってもほとんど使い道のないレアな資格です。※大型特殊第二種免許は、免許保有者全体のわずか0.002%程度!!
作業に必要な資格や免許
作業をするにあたってはそれぞれの車両に応じた“資格や免許”が別途、必要になります。
①車両系建設機械(3トン以上の建設重機を運転するために必要な特別講習)
- 整地・運搬・積込み用及び掘削用
- 解体用
- 基礎工事用
②移動式クレーン運転士免許実技教習(移動できるタイプのクレーン車を扱うための教習)
③フォークリフト運転技能講習
④けん引免許(トラクターで750kg以上の車をけん引する際に必要な免許)
教育訓練給付金でお得に取得!
「教育訓練給付金」とは、厚生労働大臣が指定した教育訓練を終了した人に、受講費用の一部を支給するというもの。例えば、10万円の講習なら2万円戻ってくるので、かなりお得!
対象者は?
✅ 現在、働いている人 → 雇用保険の被保険者期間が3年以上
✅ 離職中の人 → 雇用保険の被保険者期間が3年以上 かつ、離職後1年以内
なお、給付金を受ける場合は教習所に申し込む前に申請が必要となるので、詳細についてはハローワークに聞いてみてください。
まとめ
今回は教習所で大型特殊免許を取ってきました!
初めて乗る大型特殊車両の操縦席は、レバーや計器がズラリと並んでいて、まるでコックピット。
「こんなの本当に運転できるのか…?」とドキドキしつつ操作してみると、意外や意外!全長6m以上の大きな車両なのに、慣れてくると小回りが効いて運転しやすい!
その理由は 車体が中折れ式 だから。普通の車なら内輪差を気にしなきゃいけないところも、スイスイ曲がれて快適でした。
ただし、大型特殊免許は どこの教習所でも取り扱っている訳ではないので、事前に教習所にてご確認を!
この免許があるとフォークリフトや車両系建設機械(整地・運搬・積込み用や掘削用) の講習時間がグッと短縮されるので、持っておいて損はなし!何が起こるかわからないVUCAの時代、備えとして大型特殊免許、是非!
